SCUELデータベースとWHITE CROSS社の協力によるアンケート集計結果に基づき、歯科医院のレセコン導入傾向について分析。主要3ブランド(A社/B社/C社)傾向をまとめました。(調査時点:2024年12月)有償版レポートでは、実際のメーカー名の開示と、上記を含む250項目以上のSCUEL歯科データベース項目と比較した結果が確認できます。

1.事業所・立地特性
ブランドAは関東地方(39.0%)とその他地域(27.1%)での導入が多く、特定地域に偏らず比較的バランスよく展開されているのが特徴です。ブランドBは関西地方(26.2%)と九州地方(21.4%)で導入割合が高く、西日本を中心とした広がりがうかがえます。ブランドCは関東地方での導入が43.9%と最も高く、さらにその他地域でも34.1%と、都市部を中心に幅広い地域で展開が進んでいる様子が見られます。
| ブランドA | ブランドB | ブランドC | |
|---|---|---|---|
| 関東地方 | 39.0% | 21.4% | 43.9% |
| 関西地方 | 18.6% | 26.2% | 12.2% |
| 九州地方 | 15.3% | 21.4% | 9.8% |
| その他地域 | 27.1% | 31.0% | 34.1% |
2.医院運営・規模
ブランドAは医療法人での導入率(16.9%)がやや高く、ユニット数4台以上では42.4%と中規模医院中心の傾向が見られます。ブランドBはユニット数4台以上が57.1%と最も高く、大規模医院での導入が目立ちます。ブランドCは個人経営が68.3%と高く、小規模医院で広く使われている様子がうかがえます。
| ブランドA | ブランドB | ブランドC | |
|---|---|---|---|
| 個人 | 67.8% | 66.7% | 68.3% |
| 医療法人(2施設以上) | 16.9% | 14.3% | 19.5% |
| ユニット数(4以上) | 42.4% | 57.1% | 53.7% |
3.患者数・診療内容
ブランドAは患者数30人以上の割合が20.3%と一定数存在する一方、20人未満が11.9%にとどまり、やや中規模以上の医院での導入が見られます。ブランドBは30人以上の割合が26.2%と最も高く、多くの患者を抱える医院での利用が目立ちます。ブランドCも30人以上が26.8%と高く、いずれも繁盛医院での支持が強い傾向が読み取れます。
| ブランドA | ブランドB | ブランドC | |
|---|---|---|---|
| 患者数(19.9/日以下) | 11.9% | 14.3% | 12.2% |
| 患者数(20.0-30.0/日) | 20.3% | 9.5% | 22.0% |
| 患者数(30.1/日以上) | 20.3% | 26.2% | 26.8% |
4.経営者属性
ブランドAは院長年齢45歳以上が64.4%と比較的ベテラン層に支持されており、開業11〜20年の医院が39.0%と中堅層での利用が多い傾向です。ブランドBは院長45歳以上が69.0%と最も高く、安定した経営層に根付いています。ブランドCは若手(44歳以下)院長が29.3%、開業10年以内が34.1%と高く、新規開業や若年層の導入が目立ちます。
| ブランドA | ブランドB | ブランドC | |
|---|---|---|---|
| 院長年齢(44歳以下) | 22.0% | 16.7% | 29.3% |
| 院長年齢(45歳以上) | 64.4% | 69.0% | 56.1% |
| 開業時期(10年以内) | 16.9% | 19.0% | 34.1% |
| 開業時期(11~20年) | 39.0% | 38.1% | 36.6% |
5.医療DX・IT化への取り組み
ブランドAは光学印象(32.2%)や技工士連携加算(42.4%)に一定の導入が見られるものの、全体的にやや控えめな傾向です。ブランドBはすべての項目で4割以上と平均して高く、連携・IT化対応が進んでいる印象があります。ブランドCは医療DX推進加算が53.7%と最も高く、特にデジタル化に積極的な導入姿勢がうかがえます。
| ブランドA | ブランドB | ブランドC | |
|---|---|---|---|
| 医療DX推進体制整備加算 | 37.3% | 45.2% | 53.7% |
| 光学印象 | 32.2% | 35.7% | 34.1% |
| 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算 | 42.4% | 47.6% | 39.0% |
6.新たな制度への対応力
ブランドAは2022年導入が42.4%と最も多く、義務化前からの取り組みが目立ちます。一方、ブランドBは2021年導入が26.2%と最も早期対応が多く、制度対応力の高さがうかがえます。ブランドCは2023年5月以降の導入が26.8%と最多で、対応が遅れたユーザーが相対的に多い傾向が見られます。
| ブランドA | ブランドB | ブランドC | |
|---|---|---|---|
| オンライン資格確認 運用開始時期:2021年 | 8.5% | 26.2% | 7.3% |
| 運用開始時期:2022年 | 42.4% | 31.0% | 36.6% |
| 運用開始時期:2023年5月以降 | 22.0% | 14.3% | 26.8% |
レセコン・メーカー別傾向(まとめ)
ブランドA
中規模~大規模の歯科医院を中心に導入されており、都市・地方ともにバランスの取れた展開が見られます。ベテラン院長の比率が高く、医療法人やユニット数4台以上の施設での導入が多く、安定した経営層に支持されていると考えられます。制度対応や医療連携にも一定の反応が見られ、多機能型のオールラウンドな特性が特徴です。
ブランドB
個人経営や小規模医院での導入が多く、関西・九州など西日本での展開が目立ちます。ユニット台数や患者数は控えめで、小児歯科や若手経営層のニーズに適しています。コスト重視の傾向があり、光学印象や資格確認といった最新技術への投資は控えめで、効率を重視する医院に適しています。
ブランドC
都市部を中心に展開し、関東圏でのシェアが高いブランドです。若手院長や新規開業医院での導入が多く、30人以上の患者を持つ医院の比率も高めです。医療DX推進加算の取得が進んでおり、設備投資に前向きな傾向が見られます。成長志向・高収益を志向する医院層に強く支持されています。
本レポートは一部抜粋です
有償版では、実際のメーカー名の開示と、上記を含む250項目以上のSCUEL歯科データベース項目と比較した結果が確認できます。
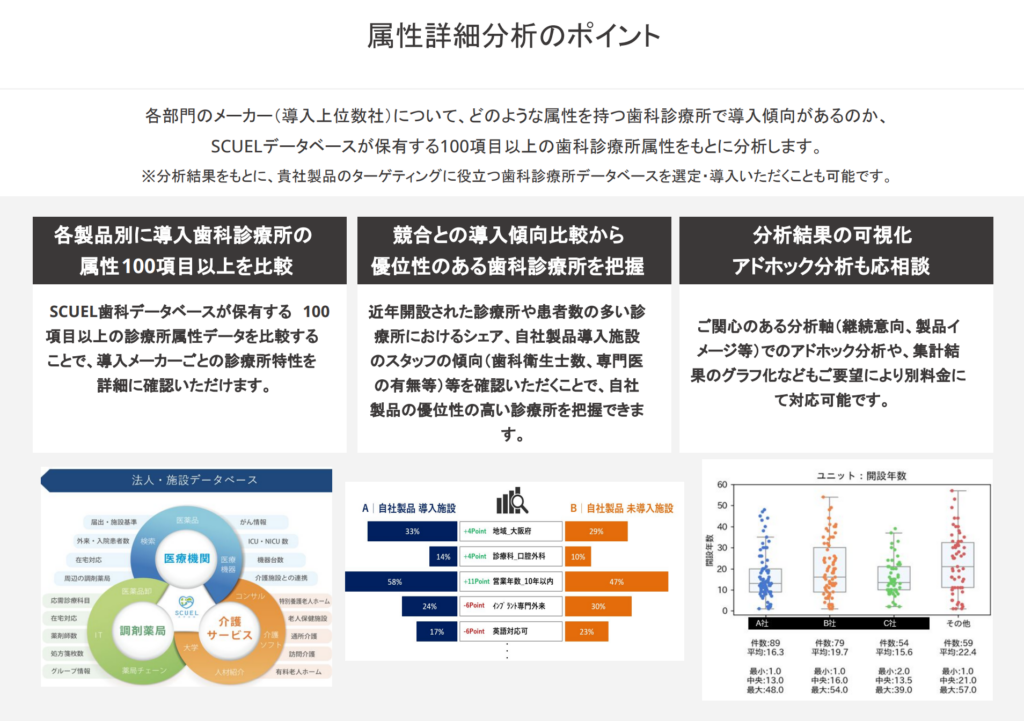
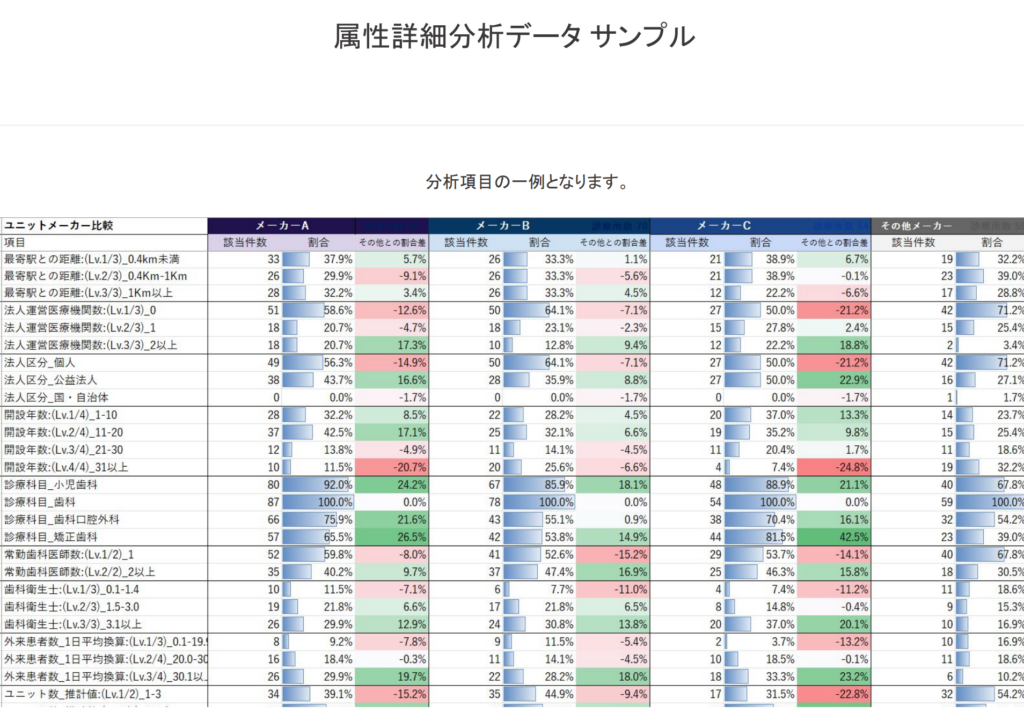
製品開発・営業ターゲティング戦略に直結するヒントを多数収録
